
iDeCo(イデコ)の運用を始めたのが2016年の7月。拠出金が運用され始めるのが中旬以降なので今で運用18ヶ月、拠出金額414,000円となりました。
iDeCoって本当にしたほうがいいの?素人に投資なんてわかんないよ?と思う方もいると思います。
私も最初はそうでした。
でも銀行に100万円預けてても80円にしかならない今の世の中。このまま年金だけにも頼れないし・・・。
ゆうちょ定期預金の満期が来た!金利を見て唖然としたので定期金利比較ランキング作ってみました!
そして猛烈に投資の勉強をして実際に投資信託や個別銘柄を買って保有してみました。今のところ相場も穏やかなほうなのでiDeCoの運用18ヶ月の損益率は15.8%、年利にすると約10%の成績となっています。

ここまで成績が伸びたのは途中でポートフォリオを見直したから。2018年1月現在のiDeCoのポートフォリオをご紹介したいと思います。
私の独断と偏見で買ってる商品なのでこれが絶対に良い!ってことじゃないからあくまで参考程度にしてみてくださいね。
SBI証券iDeCoのポートフォリオ例

私の現在のiDeCoのポートフォリオです。あくまで参考程度にね!
| 投資信託商品 | 割合 | 商品タイプ |
| EXE-i 先進国株式ファンド | 10% | 株 |
| EXE-i 新興国株式ファンド | 10% | 株 |
| ひふみ年金 | 50% | 株 |
| EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 10% | 株 |
| EXE-i 先進国債券ファンド | 10% | 国債 |
| SBI資産設計オープン資産成長型 | 10% | 株+国債+REIT |
80%は日本株、先進国株、新興国株が占めるちょっとリスク高めのポートフォリオとなっています。
私が確定拠出年金を始めた時はまだ30代。
年金を受け取るまで20年以上運用期間があるからある程度リスクを取るポートフォリオにしておかないとiDeCoは毎月手数料がかかってくるので元本保証の定期預金を選んでるとどうしてもマイナス運用になってしまいます。
今回のiDeCoのポートフォリオは20代、30代、40代前半あたりまでは株がメインの運用商品でポートフォリオを組んでみるのもいいんじゃないかな?と思います。
ただこの私の確定拠出年金ポートフォリオは20代、30代と40代向け。50代になるともう少し安全な資産運用をしたいので50%以上は元本保証の定期預金か国債での運用に変更する予定です。
iDeCoの口座管理手数料は?どこがいい?
| 手数料 | |
| 国民年金基金連合会 | 103円 |
| 事務委託手数料 | 64円 |
| 運営管理機関口座管理手数料 SBI証券 | 無料 |
| 手数料合計 | 月々:167円 年間:2,004円 |
iDeCoしたいけどどこがいい?って聞かれると私は迷わずSBI証券のiDeCoって即答します。
私がiDeCoを開設したSBI証券は口座管理手数料が無料なので他の手数料と合わせても年間の手数料は2004円。
例えば、三井住友銀行だと月々の口座管理手数料が255円かかってくるので年間の手数料は5,064円。一番高い所だと十八銀行で年間7404円もかかってきます!
これを20年間運用した場合
| 年間手数料 | 20年運用した場合 | 差額 | |
| SBI証券 | 2,004円 | 40,080円 | |
| 三井住友銀行 | 5,064円 | 101,280円 | SBI証券との差額-61200円 |
| 十八銀行 | 7404円 | 148,080円 | SBI証券との-108000円 |
SBI証券と三井住友銀行とでは20年運用した場合手数料だけで61200円もの差額が出てきます。
口座管理手数料は出来るだけ無料のところを選ぶのが大切ですけど、運用商品の品揃えのよさか、自分が運用したい商品がある金融機関を選ぶようにしましょう!
その全てを兼ね備えていたのがSIB証券のiDeCoです。
iDeCoの対象者は何歳まで?
iDeCoの対象者は専業主婦や公務員を含む、60歳未満の全ての成人が利用できるサービスです。
毎月の掛金を60歳まで積立て60歳以降に受け取ることができます。
でも50代の方はちょっと気をつけて欲しいです。なぜなら60歳の時に加入期間が10年未満の場合加入期間によって受取年齢が違ってきます。
| 加入期間 | 受取年齢 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上 8年未満 | 62歳 |
| 4年以上 6年未満 | 63歳 |
| 2年以上 4年未満 | 64歳 |
| 1ヵ月以上 2年未満 | 65歳 |
基本10年以上の加入期間(運用期間)があると受取年齢は60歳からなんですけど、それに満たない場合は60歳から受け取れないからその点は気をつけましょうね。
受取時のことも考えるとiDeCoに入ろうかな?と少しでも考えてるなら1年でも早くはいっておいたほうがいいんですよね。
あと国民年金との違いはもらえる年金は運用商品の成績次第なので、もし元本保証を選んでいいると積立金から手数料を引いた金額が年金となってしまいます。それでも節税分を考えるとお得かな。
【関連】個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)で上手に節税対策!
だから元本保証だけじゃなく20代~40代の場合、少しリスクを取った運用商品を選ぶのも大切です!
iDeCoのメリットデメリット
メリット
掛金全額が控除になる、運用期間中は非課税、引き落とし時に退職所得控除が使えると3つのメリットがあります。
あと運用成績が良いと受け取る年金も増えますね!この辺りは個人年金保険の返戻率よりは今後の景気によってはいいんじゃないかな?って思ってます(そう思いたい!)
デメリット
最大のデメリットは60歳まで引き落としが出来ません。なので途中でお金が必要になったとか、毎月のお金を拠出できないとなった時がデメリットになります。
その他には
・運用リスクは自分で
・将来受け取る年金が決まってない
・手数料がかかる(一番安い所でも年間2004円)
とか。
メリット・デメリットの詳細はこちらの記事も参考にしてみてくださいね。
【関連】個人型確定拠出年金のメリット・デメリットまとめてみました。
iDeCoは所得税住民税額控除されるの?
実際に私の給与でどのくらい税金が安くなるのが見てみたいと思います。給与は入社以来上がってないからiDeCoに入る前と入った後の年末調整を見ると一目瞭然。
| 給与所得 | 2990000円 | |||
| 社会保険料等 | 495349円 | |||
| 小規模企業共済掛金控除 (イデコの枠) | 276000円 | 0円 | ||
| iDeco有 | iDeco無 | 差額 | ||
| 所得税 | 38,700円 | 52,800円 | 14100円 | |
| 住民税 | 78,500円 | 106,000円 | 27500円 | |
| 所得税+住民税(合計) | 117200円 | 158800円 | 41600円 |
iDecoをしたほうが年間41600円もの節税が出来ています!
iDeCoは会社に控除の書類を持っていくと自分で確定申告をする必要がないから実際に節税できているのかどうかわかりにくいと思うんですけど(毎年の年末調整を保管してたら別だけど)、自分で確定申告をしてみるとどれだけ節税が出来ているのが実感できます。
iDeCo申込時の必要書類
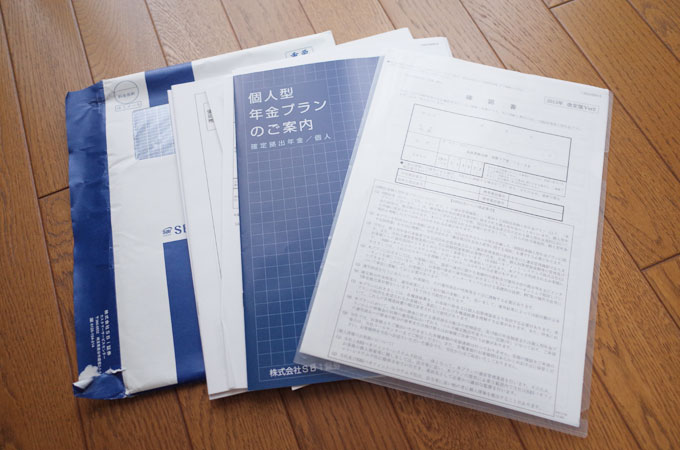
iDeCo申し込みの必要書類はSIB確定拠出年金iDeCoから資料請求をして、送られてきた資料に必要項目を記入して返送するだけです。
会社員の場合はその送られて来た書類の中に事業主の証明書もはいってるので会社にその必要項目を書いてもらって返送します。
詳しい申し込み時の必要書類や書き方はこちらも記事を参考にしてみてくださいね。
SBI証券iDeCoの引き落とし日と買付日
SBI証券のiDeCoの引き落としは毎月26日。休日の時は翌営業日。国民年金と違って分割や一括、前納や追納は出来なくて毎月口座から引き落としです。
iDeCoの買い付け日は銀行引き落とし日の12営業日(土日祝は除く)後に掛金が事務委託先金融機関(信託銀行)に送金されこの日が拠出日となって、買付日は次の日ですね。
【引き落としと買付日例】
2017年12月26日:掛金引落日
2018年1月17日:拠出日
2018年1月18日:商品購入手続き開始日
2017年1月20日以降、商品の購入手続きが完了次第、資産残高に反映
例えば先月の例だと26日に銀行から引き落としされ18日に商品購入(買い付け)がされ、20日以降に管理画面に反映されるスケジュールです。
iDeCoのまとめ
60歳まで引き落としができないデメリットはあるけども、これからの将来自分の年金を作るにはiDeCoは使わない手はない!ってくらい必要な制度だと思います。
国が公的年金は頼りにならない(また減額!?それとも70歳からの支給!?こればっかりは誰にもわかりませんね・・・)から自分の年金は自分で用意してね♪って言ってるのと同じだと思うから、これからは自分の老後の資金は自分で用意する必要がありますね。
【関連記事】
・節税効果の高い個人型確定拠出年金イデコを始めて1年経った運用成績を公開するよ!
・iDeCo(イデコ)と個人年金を徹底比較!老後の為や節税でお得になるのはどっち?
・SBIの個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)のポートフォリオにひふみ年金を追加しました!
・個人型確定拠出年金の確定申告での控除方法と必要書類をまとめてみました!
・iDeCo(イデコ)の口座管理手数料を9社から比較してみました!